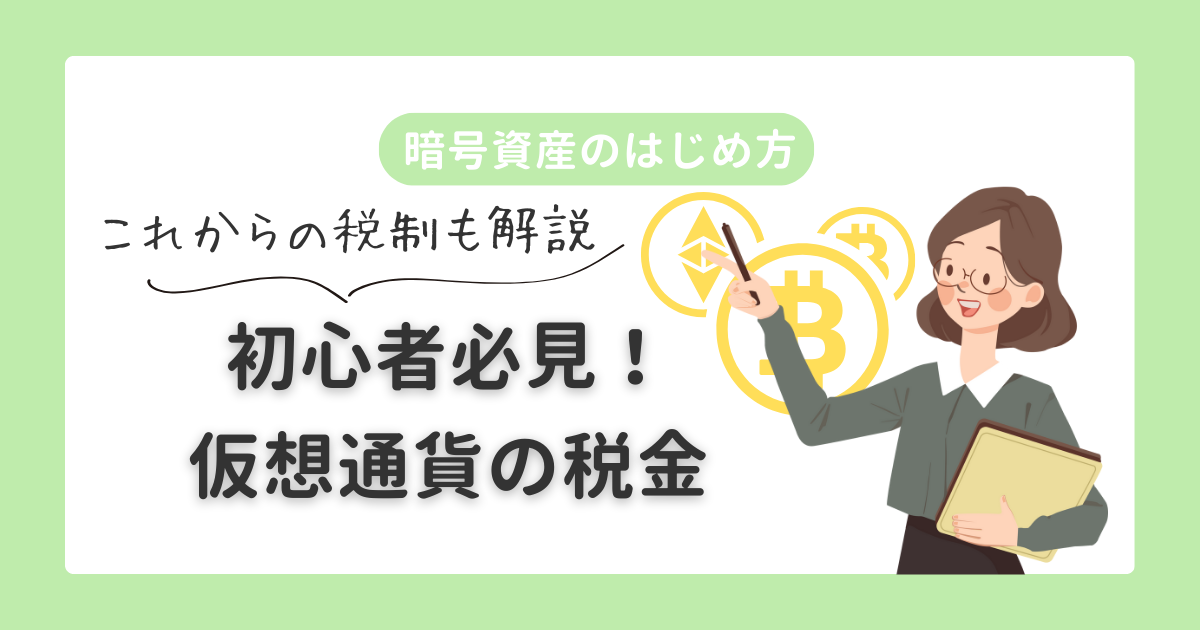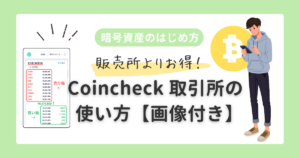税金が怖いから仮想通貨はやめておこう……
たしかに、仮想通貨の税制は株式やNISAに比べて分かりにくく、最大55%もの税率と聞くと不安になるのも無理はありません。



でも実は、しくみを整理するととてもシンプルなんです!
この記事では、初心者でも安心して理解できるように、仮想通貨の税金の基本から最新の動きまでをわかりやすく整理しました。
- 仮想通貨に税金がかかる理由
- いくら税金が取られるのか(株・NISAとの違いも)
- 税金が発生するタイミング
- 確定申告の流れ
- 2025年最新の税制改正の動き
- 意外と知らない落とし穴
最後まで読むと、仮想通貨の税金は「複雑で怖いもの」から「安心して向き合えるもの」に変わります。税金を理解して、仮想通貨を活用していきましょう!


名前 : かえ
- FP技能士2級
- 2018年〜 NISAとiDeCoでの資産形成を開始
- 2021年〜 暗号資産投資を開始
- 夫と子の3人で暮らす30代
- 家計と向き合いながら「安心して続けられる投資」を実践中
まずは基礎!仮想通貨に税金がかかる理由





仮想通貨ってお金だよね?どうして税金がかかるの?



日本の法律では仮想通貨は「通貨」ではなく「資産」として扱われているからです。
そのため、ビットコイン(=BTC)やイーサリアムを(=ETH)を売って利益が出れば「資産の売却益」として課税の対象になります。株やFXと同じく「もうけ=所得」とみなされるしくみで、国税庁が公式にルールを定めています。
ここで初心者がとくに注意しておきたいのが、「利益が出たら税金が発生する」=「確定申告が必要になる可能性がある」 ということ。知らないまま取引を続けると「税金の支払いを忘れていた!」となりかねません。
仮想通貨投資では、「利益を出す」のと同じくらい「税金への理解」が大切なのです。
具体的にどれくらい税金がかかるのか


仮想通貨での利益は、税法上の「雑所得(ざつしょとく)」に分類されます。
給与や事業所得など、他のハッキリした分類に当てはまらない収入をまとめたカテゴリーのこと。
(例:副業の一部、公的年金、FXや先物取引の利益)



雑所得は「残りものをまとめた引き出し」みたいなイメージです
そして雑所得は、給与や副業収入と合算して「累進課税」というしくみで課税されます。
累進課税の税率は所得に応じて変わる
日本の所得税は「累進課税制度」を採用していて、所得が増えるほど税率が高くなっていきます。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| ~195万円 | 5% | 0円 | 10% |
| 195~330万円 | 10% | 97,500円 | |
| 330~695万円 | 20% | 427,500円 | |
| 695~900万円 | 23% | 636,000円 | |
| 900~1800万円 | 33% | 1,536,000円 | |
| 1800~4000万円 | 40% | 2,796,000円 | |
| 4000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
雑所得は給与と合わせて課税され、利益が少ないうちは住民税込みで15%程度で済みますが、利益が大きくなると一気に税率が上がります。
合計所得…300万円
税率…10%
控除額…97,500円
<所得税>300万×10%-97,500
=202,500円
<住民税>一律10%=約30万円
合計税額約=約50万円
▶ 仮想通貨利益50万円に対しては、税金は約10万円程度の負担感です。
合計所得…700万円
税率…23%
控除額…427,500円
<所得税>700万×23%-427,500
=1,173,500円
<住民税>一律10%=約70万円
合計の税額→約187万円
▶ 仮想通貨利益150万円に対しては、ざっくり40~50万円くらいの税金となるイメージです。
たとえば副業や投資で大きく稼いだ人は、最高で45%(住民税を含めると55%)といったように半分以上を税金で取られる可能性も……。
このように、仮想通貨は大きな利益を得るほど、手元に残る金額が少なくなっていく特徴があります。



ちなみに、利益すべてに対して「55%の税金がかかる」と思っている方、意外と多いんです。利益が少なければ、税金は思ったほどかかりませんよ。
株や投資信託とは課税の区分が違う
株式投資や投資信託の利益は「分離課税」で、税金は利益に対して一律約20%です。
一方で、仮想通貨は給与と合算されて課税されるため、年収や副業収入が多い人ほど高い税率がかかってしまう仕組みです。
この違いが、初心者がとくに混乱しやすいポイントです。
たとえば、同じ100万円の利益でも——
株式なら税額は約20万円
仮想通貨なら所得次第で30万円〜55万円
と、大きな差になることがあります。
あらかじめ課税額をシミュレーションしておけば、「思ったより税金が高くて支払えない!」といったトラブルを防げます。



仮想通貨の利益は「雑所得で累進課税」という点を覚えておきましょう。
税金はいつ発生?課税タイミングを整理


仮想通貨の税金で意外と多いのが、「利益が出ている=すぐに課税」だという勘違いです。
実際には、利益を確定(=利確)したとき に初めて課税の対象となります。保有しているだけでは税金が発生すること一切はありません。
では、具体的にどのようなタイミングで税金が発生するのか整理してみましょう。
売却したとき
もっともわかりやすいのは、仮想通貨を日本円に換金したときです。たとえば、1BTCを1300万円で購入し、その後1500万円で売却した場合、差額の200万円が課税対象となります。
他の仮想通貨に交換したとき
意外と見落としがちなのが、「仮想通貨同士の交換」でも課税が発生する点です。
たとえば、ビットコインを使ってイーサリアムを購入した場合も、ビットコインを円に換金したとみなされ、差益に税金がかかります。
仮想通貨で買い物したとき
仮想通貨を使って商品やサービスを購入する場合も「使用時に利益確定」と扱われます。たとえば、購入時よりも値上がりしたビットコインでコーヒーを買った場合、その差益が課税対象です。
マイニングやステーキングで報酬を得たとき
マイニングやステーキングで新たに得た仮想通貨も、その時点での時価が「収入」として課税対象になります。これも雑所得に含まれるため、忘れずに計上する必要があります。
***
「円に換えたとき」だけではなく、交換・買い物・報酬といった場面でも税金が発生するのが仮想通貨の特徴です。
ここをしっかり理解しておけば、初心者でも思わぬ課税リスクは避けられます。
▶︎ 取引の流れ自体をイメージできると「どこで課税されるか」も理解しやすくなります。実際の購入の流れはこちらです。


確定申告は必要?しないとどうなる?


仮想通貨で得た利益は、原則、自分で確定申告をして納税する必要があります。ここを見落としてしまうと、後で大きなペナルティを受ける可能性があるので要注意です。
年間20万円を超えると確定申告が必要
仮想通貨の利益は「雑所得」に分類され、給与所得などと合算して課税されます。サラリーマンやパート・アルバイトの場合でも、仮想通貨で得た利益が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
給与収入がある人の例
会社から給与をもらっている人が副業的に仮想通貨を売買した場合、その利益が20万円を超えると確定申告が必須です。
逆に、給与収入がない専業主婦や学生の場合は、基礎控除額を超える利益(48万円以上)で申告が必要となります。
申告しないとペナルティの可能性



ほんの少額の取引だし、バレないでしょ?



海外取引所を使えばバレにくいって聞いたよ!
と申告を怠ると、後から税務署に把握されるケースがほとんどです。国内外問わず、取引所からの情報提供や銀行口座の入出金履歴など、調査手段はいくらでもあります。「バレないだろう」はもう通用しなくなってきています。
申告漏れが見つかると、ペナルティが課される可能性があります。
- 延滞税…納付期限を過ぎた分に対する利息
- 無申告加算税…申告しなかった場合にかかる追加税
- 重加算税…悪質と判断された場合に最大で本来の税額の40%



申告を怠る=余計なお金を払うリスクに直結します!
仮想通貨の利益は、たとえ少額でもきちんと申告する必要があります。給与所得がある人は「20万円ルール」を忘れずに押さえておくと安心です。
\ 税金は、仕組みを知れば怖くない /
初心者が知っておきたい確定申告の流れ





申告が必要なのはわかったけど、そもそもどうやるの…?
仮想通貨の税金で一番つまずきやすいのが「確定申告」です。



実際の流れをイメージできれば、必要以上に怖がる必要はありません。
① 誰が申告しなければならないのか
- 会社員やパートの人
-
仮想通貨の利益が年間20万円を超える場合
- 専業主婦(夫)、学生、フリーランスなど
-
利益が48万円(基礎控除)を超える場合
このラインを超えると、自分で申告が必要になります。
② 申告に必要なものをそろえる
確定申告でとくに大切なのが「正確な取引履歴」です。データや書類をしっかりと揃えましょう。
- 各取引所からダウンロードできる取引履歴(CSVファイル)
- 利益・損失をまとめた損益計算書
- マイナンバーカードや源泉徴収票など、通常の申告に必要な書類
仮想通貨は取引が多いと計算が複雑になるため、早めの整理が吉です。
③ 会計ソフトやツールを活用する
仮想通貨の取引においては、手計算で損益を出すのはとても大変です。細かく取引をする方は、仮想通貨向けの会計ソフトを利用すると効率的です。
代表的なものには、cryptact、Gtax、CoinTrackingなどがあります。取引所ごとの履歴をアップロードするだけで、自動で損益を計算してくれるので、初心者でも安心して申告できます。
④ 申告と納税
準備ができたら、国税庁のe-Taxや税務署で申告書を提出します。オンラインで完結できるため、最近はe-Tax利用者が急増中です。
申告した金額に応じて、3月15日までに納税します。納税方法は口座振替やコンビニ払いなど多様なので、自分に合った方法を選びましょう。
***
確定申告は、事前に流れを把握しておけば「未知の恐怖」から「ただの年1回のルーティン」になります。
ツールの活用は、初心者が安心して投資を続けるための強い味方です!不安のある方にはおすすめです。
▶︎ 申告や納税の不安を避けたい方は、短期の売買ではなく積立のような中長期スタイルがおすすめです。


【2025年夏 最新】仮想通貨の税制、これからどう変わる?


これまで日本の仮想通貨の税金は、「最大55%も取られる」「税金が発生するタイミングが多すぎる」と言われ、正直ハードルが高いものでした。
しかし、最近は状況が大きく変わりつつあります。業界団体や金融庁が、政府に「投資しやすい制度に変えてください!」と正式に要望を出し始めたのです。
① 業界団体の要望書「もっとシンプルで使いやすく」
2025年7月30日、国内の暗号資産団体(JCBAとJVCEA)が共同で政府に税制改正を提案しました。
内容は、投資家が「こうなってほしい!」と思うものばかりです。
- 利益にかかる税金を一律20%にしてほしい
- 損した分を翌年以降に繰り越して相殺できるようにしてほしい
- コイン同士を交換しただけでは課税しないでほしい(課税は円に換えた時点で)
これが実現すれば、



税金が高いから、売るタイミングが難しい…



交換しただけで課税されるから、動かしづらい!
という不安がぐっと減りますね。
② 金融庁まで動き出した!「もっと普通に投資できる環境に」
さらに驚きなのが、2025年8月29日、慎重派だった金融庁まで「もっと税金を軽くしてください」と要望を出したこと。
具体的な内容は、
- 税率を20%に下げる
- NISAで仮想通貨を買えるようにする
- ETFを作りやすくして、投資の選択肢を広げる
もしこれが実現したら、



仮想通貨は利益の半分が税金で消えるんでしょ…?
という不安はなくなりますね。
NISAで積み立てできたり、ETF経由で年金や大企業の資金が市場に入るようになり、日本でも「気軽に投資できる環境」に近づいていきます。
これからの仮想通貨投資はどうなる?
まだ正式に決まったわけではありませんが、2025年末に方向性は固まり、早ければ2026年からスタートすると見られています。
これからの数年で仮想通貨は、
- 株式や投資信託と同じくらい「当たり前の資産」になる
- 税金のハードルが下がって、もっと気軽に始められる
- 「売ったら課税」のタイミングもわかりやすく整理される
という未来が見えてきています。とくに「分離課税」や「損失繰越」は業界からの要望が強く、今後数年のうちに制度が変わる可能性は高いと考えられます。
税制の流れはいま、確実に投資家に有利な方向へ進んでいます。制度が整っていく過程を経験できるのは大きなメリットですし、これからの資産形成にとって大きな追い風となりそうです。
▶︎ 制度が整っていく今だからこそ、少額からコインを持ってみる体験がおすすめです。私自身も、まずは主要コイン3つから始めました。詳しくはこちらで紹介しています。


知らないと損!仮想通貨の税金で意外と見落としがちなポイント


仮想通貨の税金は「ルールを知っているかどうか」で大きな差が出ます。初心者が意外と見落としがちな落とし穴を整理しました。
保有しているだけでは課税されない
「仮想通貨を持っているだけで税金がかかる?」と心配する人も多いですが、課税されるのは利益を確定したときだけです。
税金が発生するのは、円に戻した瞬間や、別のコインに交換した時。「持っているコインの価格が上がって、いつの間にか課税対象になっていた!」となることはありません。
損益通算はできない
株や投資信託では「損失と利益を相殺(=損益通算)」できますが、仮想通貨は雑所得扱いのため、現状ではできません。
投資信託で利益を出しても、ビットコインで損失を出してしまったら、損はそのまま残ります。この違いを理解しておかないと「思ったより税金が高い」と感じることになります。
海外取引所も課税対象
「海外取引所を使えば日本の税務署にはバレない」と思っている人もいますが、完全な誤解です。
国際ルール(CARF)が導入されれば、海外取引所も税務当局に取引情報を報告するしくみになります。すでに国内でも、税務署が海外取引所の利用履歴を把握するケースは増えています。
年末にまとめて売るのは危険
12月に利益を一気に確定すると、その年の所得が一気に膨らみ、高い税率で課税される可能性があります。
もし売却するなら、複数年に分ける・計画的に利確するといった工夫が必要です。
取引履歴の管理が必須
税金計算で最も大変と言っていいのが「取引履歴の整理」。取引所によっては履歴の保存期間が短く、後からダウンロードできなくなることもあります。
- 売買のたびにエクセルなどで「日時・通貨・数量・単価・手数料・レート」を記録する
- 仮想通貨専用の会計ソフトを導入する
といったように、日頃から履歴を残しておけば、確定申告時期の自分の助けとなります。
***
「知らなかったせいで損をした!」という事態を防ぐには、こうした知識が必要になってきます。税金対策は、投資そのものと同じくらい大事な「守りの戦略」です。
▶「でも仮想通貨ってやっぱり危ない?」と不安な方は、ブロックチェーンのしくみをやさしく解説したこちらの記事もご覧ください。
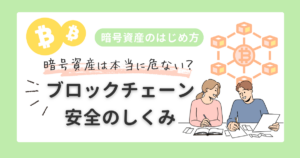
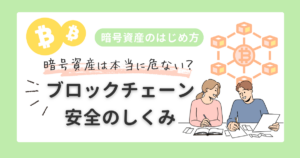
税金はしくみを知れば意外と怖くない


仮想通貨の税金は「複雑で怖い」と思われがちですが、ポイントを整理すればシンプルです。
- 課税区分は「雑所得」
- 利益が出た時点で課税される
- 20万円を超えれば確定申告が必要
- 累進課税で最大55%まで上がる可能性もある
現時点では、この4つさえ押さえておけば、大きな勘違いは防げます。
さらに、現在は「分離課税(20%)」や「損失繰越」といった投資家に有利な制度の導入も議論されています。ルールは変わっていく可能性があるからこそ、最新の動きにも目を向けておくと安心につながります。
取引履歴の管理や少額からの積み立てなど、日頃の工夫次第で「税金が怖い」という不安は大きく和らぎます。



大切なのは、税金を「投資のブレーキ」ではなく「ルールを守って安心して続けるためのもの」として捉えることです。
しくみを理解したうえで、無理のない範囲から投資を始めれば、仮想通貨はあなたの資産形成の味方になってくれるはずです。
▶︎ 筆者の「仮想通貨リアル体験談」は以下の記事で読めます。初心者ならではの失敗が盛りだくさん!これを参考にスムーズに仮想通貨を始めましょう。
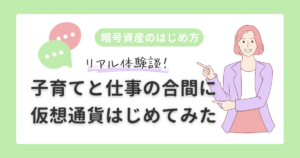
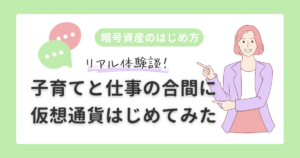
\ 税金のポイントをおさえたら /
500円から安心して仮想通貨デビュー!