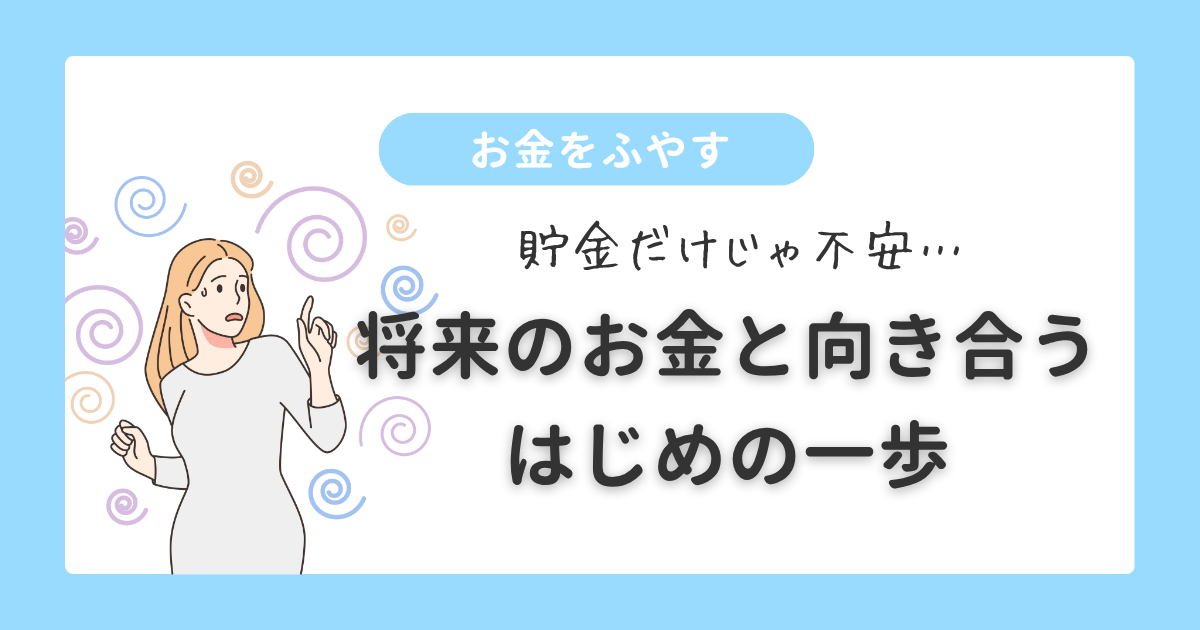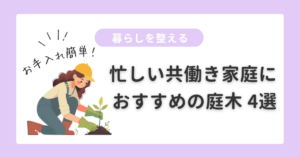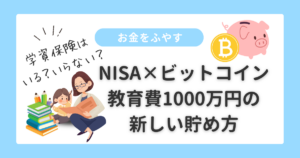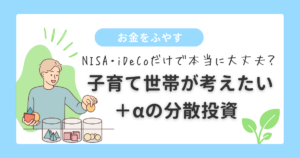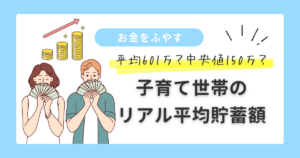貯金だけじゃ将来がちょっと不安……
こんな感覚が、心の中にありませんか?
毎月なんとかやりくりできているけれど、このままで本当に大丈夫なのか。資産形成や投資の必要性は耳にするけど「難しそう」「損をしたら怖い」という気持ちが先立って、なかなか行動に移せない。
教育費、老後資金、そして自分たちの暮らし。
将来を考えれば考えるほど、不安な気持ちが膨れていきますよね。
この記事では、同じような不安を抱える子育て世帯の方に向けて、
- なぜ貯金だけでは不安なのか
- 不安の正体を整理する方法
- 安心につながるお金との付き合い方
以上について、数字と私の実体験を交えながらお話しします。無理なく始められる方法をまとめていますので、ぜひ気軽にご覧ください。


名前 : かえ
- FP技能士2級
- 2018年〜 NISAとiDeCoでの資産形成を開始
- 2021年〜 暗号資産投資を開始
- 夫と子の3人で暮らす30代
- 家計と向き合いながら「安心して続けられる投資」を実践中
貯金だけでは将来が不安になる3つの理由


将来に向けてお金を貯めているけど、「足りなかったらどうしよう」と心のどこかがずっと落ち着かない。しっかりと貯金をしているのに消えない不安、これには3つの理由があります。
1. 物価が上がって、お金の価値が下がっている



えっ!こんなに高かった?
スーパーやドラッグストアで、いま誰もが感じていることでしょう。本当に、何もかもが高くなっています。これは気のせいではなく、はっきりと数字にも表れているんです。
総務省の消費者物価指数(CPI)によると、
- 2022年…2.5%の上昇
- 2023年…3.2%の上昇
(→ 32年ぶりの上昇幅!) - 2024年…2.7%の上昇
参考:総務省「消費者物価指数結果」
となり、この3年間で物価はおよそ9%も上昇しました。とくに食料品や日用品の値上がりが目立ち、卵やパンなどはこの1年で15〜20%も値上がりしています。
以前は100円で買えたものが今は110円以上の値段になっていて、家計全体で積み重なれば、大きな負担になります。同じ金額で買えるものが減る、つまりお金の価値が下がっているんです。
この流れが続けば、たとえ貯金額が変わらなくても、その中身は少しずつ目減りしていきます。これは、貯金だけに頼ることの危うさを物語っています。
2. 教育費や老後資金は想像以上
子育て世帯にとって避けて通れないのが、教育費と老後資金の準備です。
私自身、結婚を控えた頃、「試しにやってみよう」と軽い気持ちでライフプラン表を作成してみました。これで教育費の目安を調べて、正直なところ驚きました。
日本政策金融公庫のデータによると、高校入学〜大学卒業までにかかる費用は1人あたり約943万円*。公立・私立によって必要な額は上下しますが、少なくとも子どもひとりにつき1,000万円ほどの貯蓄を目指す必要があるそうです。
*……参考:日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」
そして老後資金。金融庁の報告書で注目された「老後資金2,000万円問題」は、当時の私は



そんなの無理!
と、びっくりしたことを今でも覚えています。
金融庁ははっきりと「公的年金だけでは足りないので、自分たちで備える必要がある」と言っているのです。しかもこの2,000万円問題、今も現実味を帯びているどころか、今後のインフレを考慮するともっと備える必要もありそうです。
そして、教育費と老後資金、この二つを同時期に準備する時期は、家計への負担が最も大きくなります。貯金だけでこの負担を支えるのは、かなり難しいでしょう。
3. 預金ではほとんど増えない
以前、1988年生まれの私が子どものころに使っていたゆうちょの通帳が見つかりました。お年玉を預けていた程度だったのですが、20万円程度の残高になんと700円弱の利息がついていました。



今では信じられませんね!
今の普通預金金利は年0.001%ほど。100万円を1年間預けても、利息はわずか10円程度です。物価が上がっているのに、お金を持っているだけではほとんど増えない。この差が、私たちのお金の価値をさらに削っていくのです。
もはや「貯金=安心」の時代は終わったと言っても過言ではありません。この現状を理解することが、将来に向けた資産形成を考える大きなきっかけになります。
お金の不安を整理してみる


将来のお金に対する不安は、「何がどう不安なのか」がはっきりしていないことが多いんです。なんとなく心配なまま時間が過ぎてしまうと、頭の中がもやもやしたままで、行動にも移しにくくなります。
まず、不安を分解してみましょう。
- 家計の不安
-
毎月のやりくりがギリギリ。急な出費やイベント費が重なると赤字になってしまう。
- 将来の不安
-
教育費や老後資金がどれくらい必要なのか見通しが立たない。そもそも準備の仕方がよくわからない。
- 知識の不安
-
投資や資産形成の知識がなく、「失敗しそう」と思ってしまう。何から始めていいか分からない。
こうして不安を言語化すると、自分が今どこでつまずいているのかが見えてきます。
家計の見直しから手をつけるのか、将来の必要な額を試算してみるのか、それとも投資の基礎知識を学ぶのか──。行動の優先順位がはっきりすれば、不安は少しずつ小さくなります。
まずは「整える」ところから
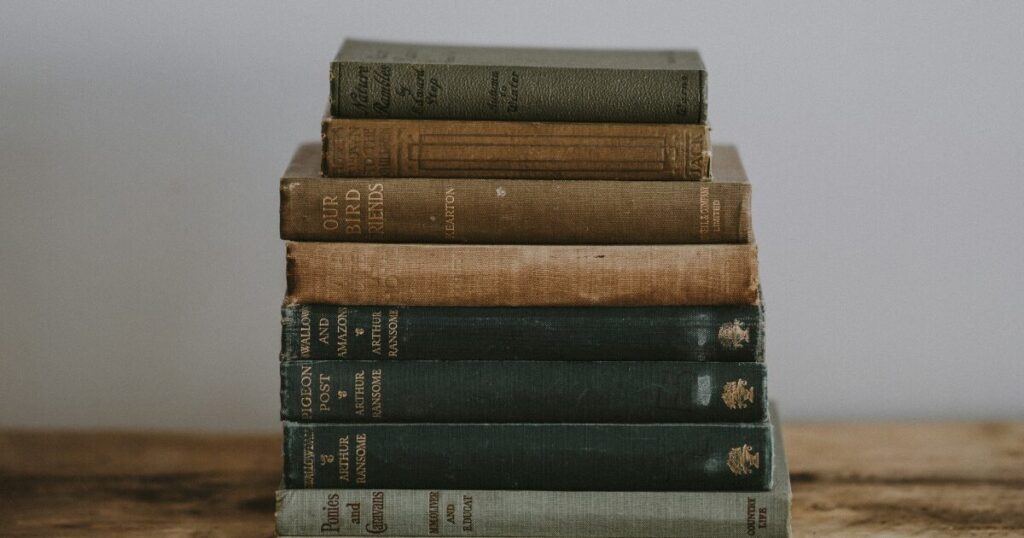
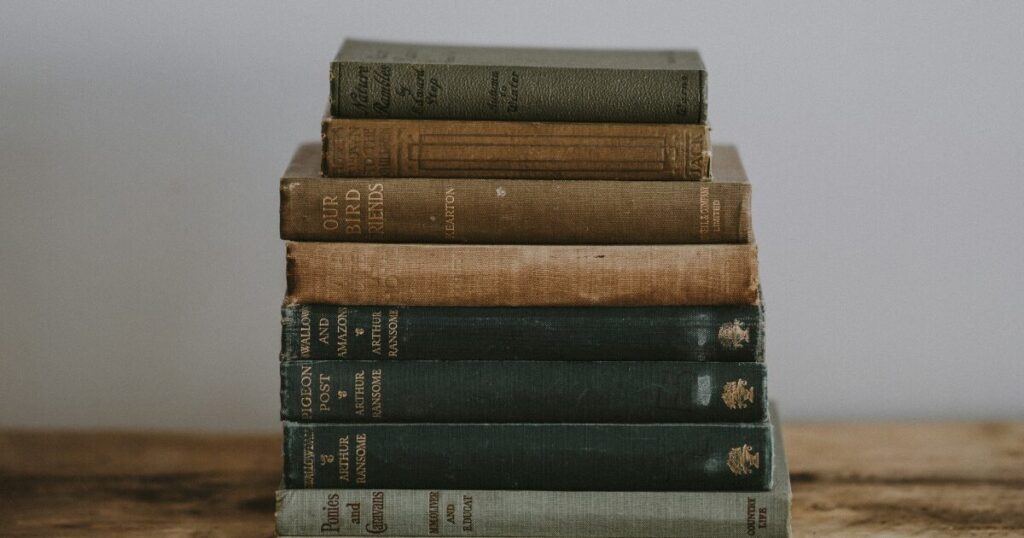
「資産形成」と聞くと、「株を買う」「FXをやる」といった大きなリスクをイメージする方もいるかもしれません。
でも、最初の一歩はそこではありません。
はじめにやるべきは、家計を整えること。
生活の中にある無駄やムラをなくして、毎月ちゃんと残せるお金を作ることが、資産形成の土台になります。
家計を整えることがなぜ大事なの?
家計を把握せずコントロールできていない場合、どうなるでしょうか?
現状が見えていない↓



いくら投資にまわせばいいかわからない
家計が赤字のまま投資↓



そもそも続けられない
余裕資金がない↓



リスクを取るのも難しい
つまり、家計が安定していない状態で投資を始めても、途中で行き詰まる可能性が高いんです。
家計を整えるための3つの基本
では「家計を整える」とは、一体どういうことなのでしょうか。大きく3つのポイントに分けて進めるのがおすすめです。
保険料、通信費、サブスクなどの毎月決まった支出を点検する。
▶︎ 小さな見直しが積み重なれば大きな効果につながります。
例)保険の特約を減らす、格安スマホへの乗り換え、使っていないサブスクの解約など
年に数回の大きな出費をあらかじめ予算化する。
▶︎ 予想外の赤字を防げます。
例)税金・車検代・進級・習い事の更新・冠婚葬祭など
収支を数字で把握する。
▶︎ 「感覚」ではなく「データ」で現実をお金の流れをつかむのが大事です。
例)家計簿アプリの利用など
家計が整うと、余裕資金を投資や貯金に回しやすくなります。「増やす」前に「整える」をやる。この順序を守ると、その後の資産形成がずっとラクになります。
私が最初にやった3つのこと(体験談)


お金の不安を洗い出して家計を整えたあとは、お金に対する不安を打ち消すために、3つのことを実践しました。
1. 固定費を見直して「残せるお金」を増やした
まず、Excelで家計簿をつけてみました。性格上、レシート1枚単位でチェックするといった細かい記録は続かないと思っていたので、頻度は月に1回のみ。その月の収入・決まって出ていく固定費・ザッと計算した変動費を記録しました。
1年ほど記録を続けてみて注目したのは「固定費」。他の固定費と比べて、とくに



スマホ代が高すぎる!
と目を引きました。
私はさっそく、スマホを8,000円から4,000円の格安プランに切り替えました。これだけで、毎月4千円の余裕が生まれたんです。その後も見直しを続けて、最終的に現在のスマホ代は月500円程度で済んでいます。
このように、スマホ代をはじめ、保険料やサブスクなどの固定費を見直すと、「なんでこんなに払ってたんだろう」という項目が意外と見つかります。
一度見直せば効果はずっと続くので、最初の行動におすすめです。
2. 少額からコツコツ積み立て投資
次に、2018年からつみたてNISAとiDeCoをスタートしました。右も左もわからない投資の世界……。



どこをみても「元本保証はないので自己責任で」と注意書きされていて、とても不安でした。
しかし、貯金だけでは不安は拭えないということをわかっていたので、書籍やネットで情報収集を重ね、お金の基本を勉強しました。
そのうえで、毎月5,000円から投資信託を購入することにしました。金額は、家計に負担をかけず「無理なく続けられる」水準です。
購入方法は、自動積み立てを設定。当時、残業の多い医療事務で勤務していたため、毎月の入金や購入手続きを自動化し、忙しい日々の中でも継続できる環境を作りました。
投資は時間を味方につけることがポイントなので、この「継続の仕組み化」は欠かせません。自動積立に設定すれば、忙しい日常の中でも忘れずに続けられます。
「投資=難しい」というイメージを持っていた私でも、少額から・自動積み立てで始めたおかげでハードルが低く感じられました。
3. 「小さなチャレンジ」で暗号資産を購入
最後に、2021年に暗号資産(仮想通貨)を10万円分だけ買ってみました。これは家計の資産形成とは別で、自分の貯金の一部を使った小さなチャレンジです。



と言っても、「なんかすごい価格が上がってる」と気になっただけの単純な動機でした。笑
投資信託と比べると値動きは激しいですが、少額なら心理的負担は小さく済みます。それに、持ち始めると自然とニュースや市場の動きに関心が向くので、学びにもつながったのも副産物でした。
素人なりにブロックチェーンという技術やビットコインの仕組みにも興味を持ち、将来性を感じるようになり、少しずつ買い増しし、現在は長期的な資産の一部として保有しています。
▶ 仮想通貨の安全を守る「ブロックチェーン」のしくみについてはこちらの記事で解説しています。
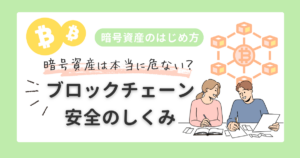
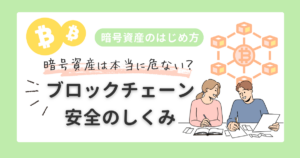
これら3つの行動は、どれも「完璧にやらなきゃ」ではなく、できる範囲からのスタートでした。やりながら少しずつ行動を重ねた結果、将来に対する漠然とした不安が少しずつ薄れていきました。
私の中で「なんとかなるかも!」という気持ちが芽生えたのは、この一歩を踏み出したからだと思います。
\ 500円から安心スタート /
子育て世帯が始めやすい資産形成


家計と将来の両方を考える子育て世帯にとって大切なのは、無理せず、でも着実に資産形成を進めることです。3つのステップにまとめてみました。
1. 家計を見直す
資産形成の土台づくりは、家計を整えることから。
とくに、保険・通信費・サブスクは見直し効果が出やすい項目です。保険や通信費、使っていないサービスなどを見直し、毎月の支出を軽くします。浮いた分はそのまま投資や貯金にまわします。
▶︎ 私がスマホ代を7,800円削減した方法など、スマホでできる固定費削減術をまとめています。
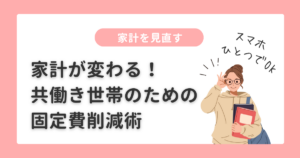
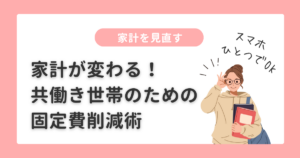
2. 長期積み立てで堅実に増やす
NISAやiDeCoは、長期・分散・積立という投資の基本を押さえた制度です。少額から始められるため、初心者でも取り入れやすく、税制面のメリットもあります。
毎月の積み立て額は、家計の負担にならない範囲が基本です。こうした制度をしっかりと活用し、長期的に続けていけば、時間を味方にしながら資産を育てていけます。
▶︎ NISAのはじめ方や、NISAとiDeCoとの違いは、以下の記事でまとめています。
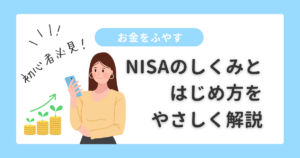
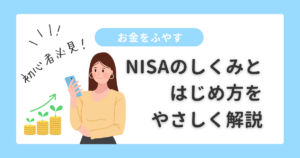
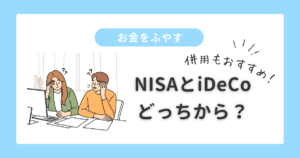
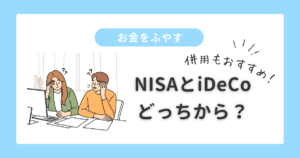
3. 少額で新しい投資にも触れてみる
興味があれば、暗号資産のような新しい資産クラスに少額だけ挑戦してみるのもひとつの方法です。全体の1〜5%程度にとどめれば、リスクを抑えつつ経験が積め、見える世界も広がりますただしこれはあくまで家計とは別枠の「チャレンジ枠」にするのがおすすめです。
▶︎ 暗号資産は子育て世帯にも有効な投資の選択肢です。理由やはじめ方の記事もぜひ参考にしてみてくださいね。
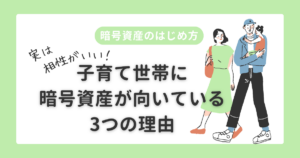
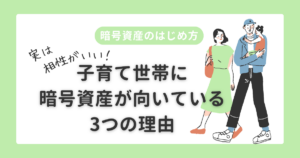


こうした方法をバランスよく取り入れると、リスクを抑えながら将来への備えができます。



小さく始めて、継続できる仕組みを作ることが何よりも大切です。
最初の一歩は小さくていい


貯金は大事です。
でも、物価上昇や教育費・老後資金という今の日本の現実をみると、貯金だけでは心もとない時代になってきています。
いきなり大きな投資や難しい運用をする必要はありません。
こうした小さな一歩の積み重ねが、未来のお金の不安を減らし、家族の安心につながっていきます。
完璧じゃなくていいんです。
お金の不安を、あなたの今日の小さな行動で、数年後の大きな安心に変えていきましょう!



このブログでは、初心者にもわかりやすく「お金と暮らしを整える方法」をお伝えしています。
興味のあるテーマから、ぜひ読んでみてくださいね。
忙しい毎日でも、無理なく一緒に整えていきましょう!
\ 最短1日で口座開設 /
少額から暗号資産をはじめてみる